安来市の未来を担う、産業振興と人材確保、そして観光振興のシナジー効果(安来市政の課題は?)

安来市は、スマートインターチェンジの新設や出雲村田製作所の進出など、新たな産業振興の局面を迎えています。しかし、同時に人口減少や働き手不足といった課題も抱えています。これらの課題を解決し、持続可能な地域社会を実現するためには、産業の振興、働き手の確保、観光産業への取組みの三つの側面から総合的な戦略を構築することが不可欠と言えます。
◎産業の振興
多様な産業の集積と地域経済の活性化
出雲村田製作所の進出は、安来市に新たな雇用を生み出し、地域経済の活性化に大きく貢献することが期待されます。しかし、一企業に頼りきりになるのではなく、多様な産業を誘致し、産業構造の多角化を図ることが重要です。
○中小企業の育成
地域に根ざした中小企業の育成を支援し、多様な製品やサービスを提供できる産業構造を構築する。
また、スマートインターチェンジ周辺には、物流拠点や商業施設の集積地を形成し、産業クラスターを構築することで、雇用創出効果を最大化することができます。
○先端産業の誘致
出雲村田製作所のような電子部品製造業を誘致することは大切なことです。ただそれだけでなく、IoTやAIといった先端技術を活用した企業の誘致も積極的に進めるべきです。
特に山陰のほぼ中央にあり中海・宍道湖・大山圏域の中心部にある安来のメリットを活かして、大型の物流センターや、AIに欠かせないデータセンターを誘致する工夫も必要ではないだろうか。
○地域産業の活性化
地域の伝統工芸や農林水産品といった地域資源を活かした産業を育成し、高付加価値化することで、地域経済の活性化を図るべきです。
また、地域産品の製造・販売や、観光産業との連携による新たなビジネスモデルの創出も考えられます。例えば、地元の特産品を使った加工食品の製造や、観光客向けの体験型プログラムの開発など、地域資源を活かした産業振興は、地域住民の生活を豊かにし、定住促進にもつながります。
◎働き手の確保
若者の人口減少に歯止めをかけ、多様な働き方を支援
安来市の人口減少は、若者の流出が大きな要因となっています。この問題を解決するためには、若者が地元で働き、生活できるような環境を整える必要があります。具体的には、以下の施策が考えられます。
- 教教育環境の充実
高校生に対する進路指導の強化や、地元企業との連携によるインターンシップの実施など、若者が地元で働くことを身近に感じられるような取り組みを進める。 - 子育て支援の充実
保育所の整備や、子育て中の親を支援する制度の拡充など、安心して子どもを育てられる環境を整える。 - 多様な働き方の支援
テレワークや副業の推進、外国人による地域おこし協力隊の活用など、柔軟な働き方を支援することで、地域外からの移住を促進する。 - 女性活躍の推進
女性の就業率向上を図り、多くの女性が社会で活躍できるよう官民あげて取り組む。 - 外国人労働者の受け入れ
労働力不足は、避けては通れない問題になるのは明らかで、外国人労働者の受け入れを積極的に、且つ早急に検討し、多様な人材の活用を促進する。
特に、女性の社会活動への参画を促進することで、多様な目線で活躍できる社会の実現を目指すべきです。
◎観光産業への取組み
足立美術館の集客力を最大化し、新たな観光資源を創出
足立美術館は、安来市の貴重な観光資源ですが、他の観光地の集客力が低いという課題があります。
足立美術館の集客力を最大限に活かし、周辺地域の観光地との連携を強化することで、観光客の滞在時間を延ばし、消費を増やすべきです。
この課題を解決するためには、以下の施策が考えられます。
- 観光ルートの開発
足立美術館を起点とした観光ルートを開発し、周辺の観光地との連携を強化する。例えば、月山富田城跡や安来清水寺を結ぶ歴史文化散策コースや、自然豊かな地域を巡るサイクリングコースなどを開発する。
月山富田城跡においては、戦国大名・尼子氏や家臣である山中鹿之介を題材にした現在の歴史資料館を、段差の無いバリアフリーの資料館に改装し、安来清水寺においては、厄払いの寺と三重塔や中海を望む展望台を主体にした観光ルートを企画し、そして自然豊かな中海沿岸をゆったりと走るサイクリングコースなどのルートを開発して見てはどうだろう。 - 観光情報の発信
SNSやウェブサイトを活用し、積極的に観光情報を発信する。特に、海外からの観光客の誘致を視野に入れ、多言語対応の観光案内サイトを整備する。そして、安来節演芸館を利用して安来節だけでなく神楽・歌舞伎・落語・漫才など多彩な催しで集客をはかる。
その中でも、安来節演芸館を劇場として歌舞伎公演を誘致し、足立美術館とセットでツアーを組み、都会からお客様を呼び込むなど、積極的に企画し催しをはかるべきです。 - 体験型観光の推進
地域の文化や歴史に触れることができる体験型の観光プログラムを開発する。
例えば、松源寺での「河井寛次郎ゆかりの焼物鑑賞と座禅の体験」ツアーや、神話の女神イザナミノミコトが眠る比婆山久米神社奥の宮の「比婆山のイザナミ参拝」ツアー、「醤油と金山寺味噌づくり体験」ツアー、及び清水の「精進料理と鷺の湯温泉の宿泊」ツアーなど、安来の地域資源を有効に活用した催しを考案してはどうだろうか。 - 観光インフラの整備
観光客が快適に滞在できるよう、交通アクセスや宿泊施設、飲食店・土産売店などの観光インフラを整備するべきです。
京都などの観光地の参道沿い飲食店・土産売店までは行かないまでも、安来清水寺の駐車場周辺や、月山富田城跡の河周辺にある道の駅「広瀬・富田城」などを整備し、清水ようかんと赤江地区のイチゴやメロンなどのフルーツを使用したスイーツ「やすぎの色葉(いろは)」や、小豆と比田地区のもち米を使用した「比田ぜんざい」など、安来の特産品を使用してアレンジした食べ物や土産品を、飲食店や土産売店で販売して集客できる工夫を行なってみてはどうだろうか。 - 地域住民の観光意識の向上
地域住民が観光客に対して積極的に接客できるよう、観光に関する「おもてなしの心」を育む、研修会を実施する。
その中でも、世界的に有名な足立美術館には、国内はもとより国外からも多くの観光客が訪れますので、地元でボランティアガイドを募り、海外観光客向けの英語・韓国語などの会話研修会を行うことで、安来の観光情報を伝えたりSNSで発信したりできる可能性があります。
また、地域住民が主体となって観光資源を開発・運営するような仕組みづくりも重要です。例えば、地域住民が運営する観光案内所を設置したり、地元の特産品を使ったお土産品を開発したりするなど、地域全体で観光振興に取り組むことが大切です。
◎三つの側面を連携させた総合的な戦略
産業振興、働き手の確保、観光産業への取組みの三つの側面は、相互に関連しており、それぞれが他の側面を補完し合う関係にあります。
例えば、
①産業の振興(企業誘致)によって雇用が創出されれば、
②雇用のあるところに人は集まるので、働き手の確保(定住促進)が容易になり、
③人口が増えれば観光産業の活性化(観光振興)にもつながります。
また、観光産業の活性化は、地域の魅力向上につながり、人材の定着率を高める効果も期待できます。
これらの側面を連携させた総合的な戦略を策定し、実行していくことが、安来市の持続可能な発展には不可欠だと考えます。
◎今後の展望
安来市は、スマートインターチェンジの新設や出雲村田製作所の進出など、新たな発展の機会を迎えています。しかし、同時に人口減少や働き手不足といった課題も抱えています。これらの課題を克服し、魅力ある地域社会を実現するためには、市民、企業、行政が一体となって、長期的な視点を持った取り組みを進めていく必要があります。
具体的には、以下の取組が重要になります。
- 地域ビジョンの策定
将来の安来市の姿を描き、20ヵ年計画等の長期スパンで具体的な目標を設定する。 - 関係機関との連携強化
地域の企業、大学など教育機関、NPOなど関連団体、様々な関係機関と連携し、課題解決に向けて共同で取り組む。 - 市民参加の促進
市民が主体的に地域づくりに参加できるような仕組み(有償ポランティア活動など)を構築する。 - 柔軟な対応
社会情勢の変化に対応するため、常に戦略を見直し、早めに改善していく柔軟な体制づくりが望まれます。
◎まとめ
安来市政が抱える課題は、一朝一夕に解決できるものではありません。しかし、①産業の振興、②働き手の確保、③観光産業の取組みという3つの柱を軸とした総合的な取り組みを継続的に行うことで、持続可能な地域社会を実現することが可能だと考えます。
安来市の未来は、市民、企業、行政が協力し合って創られていく事を期待しています。
@語意
⭕️シナジー効果とは、
複数のものが相互に作用し合い、単独で活動したときよりも大きな効果が生まれることを指します。ビジネスシーンでは、複数の企業や事業を統合したり、社内の部署が協力したりすることで、相乗効果を生み出すことを意味します。
⭕️産業クラスターとは、
特定分野の企業や大学、研究機関、関連機関などが地理的に集積し、競争と協力を通じて新たな付加価値(イノベーション)を創出する状態を指します。
産業クラスターの形成には、次のような要素が重要です。
- 「知恵」の場としての大学・研究所(知識力)
- イノベーションを育む「多様性」(変革力)
- 「カベ」を乗り越える力(連携力)
⭕️有償ボランティアとは、
ボランティアとは自発的な自由意志によって、何らかの社会奉仕活動をすることを指す言葉であって、有償無償は問われません。
日本ではボランティアというと、「手弁当で無料奉仕」のような、ボランティア=無料だという発想ばかりが先行していますが、それは違います。ボランティアには、無償ボランティアと有償ボランティアがあります。
ただし、有償ボランティアといっても賃金は「謝礼」程度(交通費や食費など自治体、地区によって相場があるようです)で安く、あくまでも人の役に立とうというサービス精神に根ざさないと、労働に対する対価だけ考えたらアルバイト(最低賃金以上の時給)の方がいいでしょう。
割りに合わない低賃金であることを承知の上で、それでも困った人の為に一肌脱いであげましょうという、善意に基づいて仕事をするのが有償ボランティアです。
仕事をしてもらう方も、労働してもらったらお金を払うのは当たり前という感覚が必要です。
◎「有償ボランティアの場合、労働基準法適用外により労災保険や雇用保険の加入が不要であり、受け取る金銭は「謝礼」にあたるため最低賃金法も適用外とされます。」
ですので、定年退職されて年金で生活されているような方や、学生さんが、自分の空いた時間を利用して、困っている人の為に働きたいと言う、自発的な自由意志を持った人に向いた働き方が、有償ボランティアだと思います。



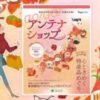






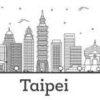


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません