鳥取県南部町の「リフォーム体制一元化」政策における、安来市民からの視点

鳥取県南部町が打ち出した住宅リフォーム体制の一元化は、隣接する安来市民の目から見ても、喫緊の課題解決に向けた先進的で意欲的な取り組みだと感じます。
特に、耐震化という喫緊の課題に対し、無料診断の実施、相談から施工、補助金申請までをワンストップで提供する体制構築は、町民の負担を軽減し、リフォームへのハードルを大きく下げる効果が期待できるでしょう。
◎南部町の政策実行力と町民の期待
今回の連携協定に見られるように、南部町が全国的なノウハウを持つ「全国住宅産業地域活性化協議会」や地域に根差した「なんぶ里山デザイン機構」と連携し、具体的な事業計画と予算措置を迅速に進めている点は、その政策実行力の高さを物語っています。南部町長自らが「低価格で実現する組織に向けて一歩踏み出せた。」と語るように、トップダウンで明確な目標を掲げ、関係各所との連携をスムーズに進めるリーダーシップは、この政策の実現を大きく後押しするでしょう。
また、無料耐震診断の対象を旧耐震基準で建築された住宅に絞り、具体的な戸数と予算を明示している点も、計画の具体性と実現可能性を高めています。延べ床面積280平方メートルの住宅で一軒あたり20万円という費用感も、町が一定の経済的負担を覚悟しつつ、町民のニーズに応えようとする姿勢の表れと見受けられます。
さらに、空き家対策にも取り組む「なんぶ里山デザイン機構」を相談窓口とし、耐震化だけでなく、断熱化や太陽光パネル設置といった現代的なニーズにも対応する姿勢は、町民の幅広い期待に応えるものと言えるでしょう。設計・施工業者とのマッチングという機能も、リフォームを検討する住民にとって、信頼できる事業者選びの負担を軽減する重要な要素となります。
町役場の各課(①総務課②町民生活課③建設課④未来を創る課)が連携し、補助金申請を一元的に受け付ける体制も、縦割り行政の弊害を排し、住民サービスの向上を目指す意欲的な試みです。複数の窓口を行き来する煩雑さを解消することで、住民はよりスムーズに支援を受けられるようになり、リフォームへの意欲も高まることが期待されます。
津山町長の「役場の職員が訪問して、悩みや不安を聞く仕組みを作り上げたい。」という言葉からは、行政が単に制度を提供するだけでなく、住民一人ひとりの状況に寄り添い、きめ細やかなサポートを目指す姿勢が伺えます。
これは、高齢化が進む地域においては特に重要な視点であり、住民の安心感を醸成する上で大きな意味を持つでしょう。
◎安来市の現状と市民感覚への隔たり
一方、隣接する安来市においては、住宅の耐震化やリフォームに関する一元的な支援体制は、少なくとも現時点では明確には打ち出されていません。個別のリフォーム業者や設計事務所への相談、あるいは住宅関連の補助金制度が断片的に存在する状況であり、南部町のような包括的な取り組みは見られません。
安来市民の感覚としては、住宅の老朽化や耐震性への不安は潜在的に存在しているものの、どこに相談すれば良いのか、どのような支援制度があるのかが分かりにくいという声も聞かれます。特に高齢者層にとっては、複雑な申請手続きや複数の業者とのやり取りは大きな負担となり、リフォームを諦めてしまうケースも少なくないと考えられます。
また、安来市においても空き家問題は深刻化しており、これらの空き家の多くは旧耐震基準で建てられたまま放置されている可能性があります。
南部町の取り組みと比較すると、安来市においては、住宅リフォームに関する情報提供や相談体制が十分に整備されているとは言えません。また、複数の課が連携して補助金申請をサポートするような体制も確立されていないように見受けられます。この点が、南部町の積極的な姿勢と、安来市の現状との大きな隔たりと言えるでしょう。
安来市民としては、南部町の取り組みを参考に、より住民に寄り添った、分かりやすく利用しやすい住宅リフォーム支援体制の構築を望む声も少なからずあります。特に、高齢化が進む安来市においては、相談窓口の一元化や申請手続きの簡素化、さらには訪問による相談支援などは、非常に有効な施策となる可能性があります。
◎まとめ、と安来市への提言
鳥取県南部町の「リフォーム体制一元化」政策は、明確な目標設定、関係機関との連携、具体的な予算措置、そして住民に寄り添う姿勢において、高い政策実行力と町民の期待が感じられる先進的な取り組みです。
一方、隣接する安来市においては、住宅リフォームに関する一元的な支援体制は未整備であり、情報提供や相談体制、補助金申請手続きなどにおいて、改善の余地が大きいと言わざるを得ません。安来市民の住宅の老朽化や耐震性への不安、そして空き家問題の深刻さを考慮すると、南部町の取り組みは、安来市にとって貴重な示唆を与えてくれるでしょう。
安来市においても、南部町の事例を参考に、以下の点について検討を進めることが望まれます。
- 住宅リフォームに関する相談窓口の一元化
空き家対策に取り組むNPO法人や地域包括支援センターなどを活用し、耐震化、断熱化、省エネ化など、住宅に関するあらゆる相談をワンストップで受け付ける体制を構築する。 - 無料耐震診断の導入
特に旧耐震基準で建てられた住宅を対象とした無料耐震診断を実施し、住民の防災意識を高めるとともに、具体的なリフォームへの動機付けを行う。 - リフォーム補助金制度の拡充と申請手続きの簡素化
耐震化や省エネ化リフォームに対する補助金制度を拡充し、オンライン申請や窓口での一括申請など、住民が利用しやすい申請手続きを導入する。 - 関係各課の連携強化
都市整備課、福祉課、環境政策課など、住宅リフォームに関わる複数の課が連携し、情報共有や共同での支援体制を構築する。 - 地域事業者との連携
地元の設計事務所や工務店と連携し、住民のニーズに合ったリフォームプランの提案や施工を支援する体制を構築する。 - アウトリーチ活動の実施
高齢者世帯や情報弱者に対して、住宅リフォームに関する情報提供や相談支援を積極的に行うための訪問活動などを検討する。
南部町の取り組みは、地域住民の安全・安心な暮らしを守り、住みやすいまちづくりを進める上で、非常に重要なモデルケースとなる可能性があります。
安来市においても、この先進的な取り組みを参考に、地域の実情に合わせた住宅リフォーム支援体制を構築することで、市民の生活の質の向上に繋がるのではないでしょうか。
<語意>
◯アウトリーチ活動とは、
支援が必要な人に、自ら支援を求めるのが難しい、あるいは支援の必要性を自覚していない場合に、支援機関や専門家が積極的に働きかけて、情報や支援を届ける活動のことです。
社会福祉や医療の分野でよく用いられ、地域住民とのコミュニケーションを深め、支援の輪を広げることを目的とします。







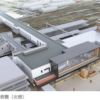


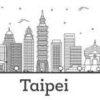


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません